浴衣話その2〜用途としての浴衣〜
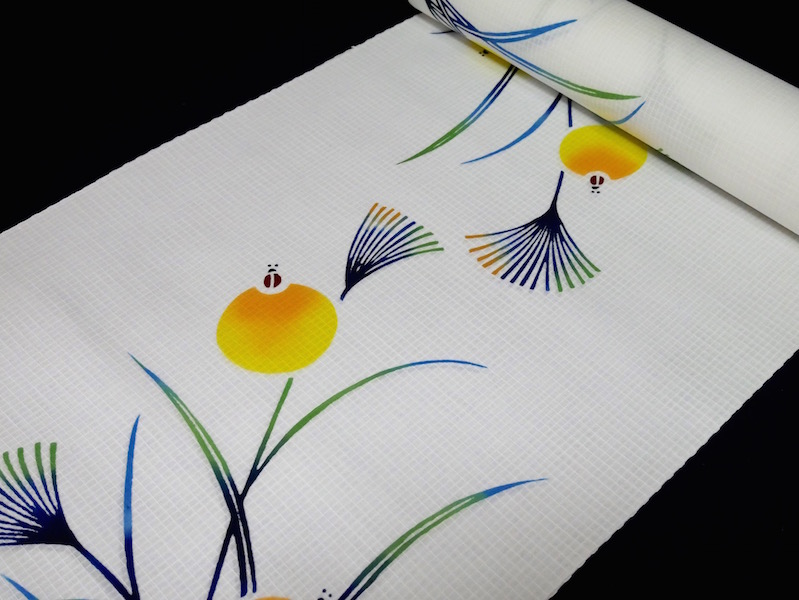
さて、前回に引き続いて浴衣の話。
あ、結論だけ知りたいという方は、文頭と文末だけ読んで頂ければ大丈夫です。
早速ですが、今回の結論はこちらです!
ドンッ!!
現在、浴衣と呼ばれる物には大きく2種類。
「生地の種類としての浴衣」と「用途としての浴衣」
があるんです。
ナンノコッチャ?
では前回はおさらいから始めましょう。

基本的に浴衣の生地は
1,手ぬぐいと似たような触り心地の木綿の生地で
2,「絞り」や「注染」。「型染め」といった技法で後から染められた物
ただし、成り立ちからいうと「綿100%」だけでなく「麻」を用いた生地は浴衣生地の1種。
ということでした。
これが「生地の種類としての浴衣」です。
で、ここからが今日のお話。
浴衣にはもう1つ「用途としての浴衣」という見方があるんです。
ナンノコッチャ?
皆さんが「浴衣と着物の違いってなんですか?」と質問をした時に
高確率で帰ってくる答えは「着用方法が違います」
ではないでしょうか?
乱暴に言えば、
長襦袢を着てから着る→夏きもの
肌着や素肌の上の直接着る→浴衣
これって、着用方法の違いだけで、その物ズバリが浴衣地なのか着物地なのか
明言されてないですよね。
そうなんです。
めちゃくちゃ乱暴に言ってしまいますが、この定義でいけば
「長襦袢を着なけりゃ、すべての物は浴衣である」
と言うわけです。
そんな馬鹿な・・・です。
いくら何でも「振袖」や「留袖」を長襦袢無しで着用して
「浴衣です!」なんて人はいません。
ではなんなのか。
私はこう解釈します。
「浴衣ではないけれど、浴衣風に着用しても違和感がない物」。
つまり夏きものや、綿きものとして生まれているけれど
浴衣風に着用しても違和感がない雰囲気なので
浴衣として販売されたり、
「浴衣としても着用できます」と販売されたりする物。
これらも広い意味で「浴衣」として扱われているわけです。
「備前焼」のような物の成り立ちとしての「浴衣」と
「湯のみ」のような使用方法としての「浴衣」が同じように語られたら・・・。
そりゃ、浴衣の定義がどんどん分かりにくくなりますよね。
それが今の状況なんじゃないでしょうか。
では、広い意味での「浴衣」と「夏きもの」。
その違いはまた次回!
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。










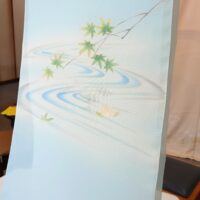


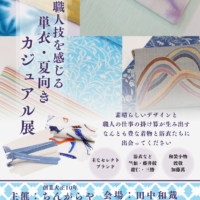

この記事へのコメントはありません。